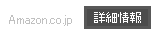5年以上前の古いパソコンの起動をたった5000円で超快速にする方法
2024-03-09
皆さんは今お持ちのパソコンを何年くらい使い続けているでしょうか。インターネットやSNSを使ったり、音楽や動画を楽しむくらいの利用であれば、数年前のパソコンでも特に問題なく使えているかと思います。
しかし、パソコンの起動やブラウザの立ち上がりに時間がかかったりして多少のストレスを感じる時があったりするかもしれません。
ただ、とりあえず使えてはいるので何万円もかけて新しいパソコンに買い替えるほどではないかなと我慢している人も多いのではないでしょうか。
そのような悩ましい状況をたった5000円で改善してキビキビ動くパソコンにする方法を紹介したいと思います。
数年前のパソコンを今でも利用している人は意外と多い
最近では第15世代インテルcoreプロセッサが発表されるなど、日々パソコンの性能が向上しています。
しかし、多くの人はインターネットやSNS、メールや動画視聴などが主な利用目的だと思いますので、最新の高性能パソコンを買ってもその性能を100%使う機会はあまりないのではないでしょうか。
私が現在所有しているパソコンのなかにも9年前に購入したデスクトップPCがあるのですが、動画編集作業などCPU負荷が大きい作業はさすがに時間がかかって厳しいものの、インターネットやメールを見たり、音楽や動画を楽しむ程度の利用は問題なく使うことができています。
それでも最近購入したパソコンと比較すると、例えば起動してから使用できるまでにかかる時間が新しいパソコンが20秒弱なのに対して1分以上かかってしまうなど、動作の遅さに多少のストレスを感じることがありました。
パソコンの性能差や個々の状況によって違いはあるかと思いますが、同じように古いパソコンの動作の遅さにストレスを感じている人も多いのではないでしょうか。
SSD換装でパソコンが見違えるほど激速に
そこで、パソコンの動きを比較的手軽に速度アップできることから最近人気が高まっている「SSD換装」をやってみました。
SSD換装とは、パソコン内のWindowsシステムやデータなどを保存しておくHDD(ハードディスクドライブ)というパーツを、SSD(ソリッドステートドライブ)というHDDよりもデータの読み書き速度が数倍速いパーツに交換する作業のことです。
結果から先に言うと、起動やシャットダウンにかかる時間が最近買ったパソコンと同程度にまで短縮され、ブラウザやWord・Excelなども以前よりあきらかに早く起動するなど、期待以上の成果を得ることができました。
SSDは十数年前からありましたが、HDDと比べると価格が高く、保存できるデータ容量も数十GBのものが主流だったため、一般的なものではありませんでした。
しかし最近になって低価格化が進み、500GBや1TB以上の大容量SSDも登場してきたことで、HDDよりもデータの読み書き速度が速く音が静かなどの特長もあって特に注目されるようになりました。
また、3~4万円程度の比較的低価格なパソコンにも標準でSSDが組み込まれているモデルが出てきたことからも、SSDが費用対効果の高い一般的なパーツになりつつあることがわかります。
価格面でも、例えば500GBのSSDが4000円台から、大容量の1TBでも6000円台から買えるなど、かなり手頃になってきました。
このSSDを使って数年前のパソコンを安く効果的にキビキビ動くパソコンにする方法を、古いデスクトップパソコンを事例に紹介したいと思います。
SSDをパソコンに取り付ける手順
まず、パソコンにSSDを取り付ける手順ですが、基本的な作業の流れは以下のような感じです。
①パソコンにSSDを接続する。
②WindowsがインストールされているHDDのデータをまるごとSSDにコピー(クローンを作成)する。
③コピー元のHDDを取り外し、作成したSSDを取り付ける。
パソコンの種類やデータ容量など個々の利用状況によって多少変わる場合がありますが、SSD換装作業は基本的には上記のような流れになると思います。
では、具体的な作業方法について説明していきます。
・パソコンにSSDを接続する
まず、現在正常に動いているWindowsのシステムデータをまるごとSSDにコピーするための準備として、SSDをパソコンに接続します。
今回作業したデスクトップパソコンの場合、内蔵されているHDDやSSDは電源用コードとデータ接続用のSATAコードの2本で接続されており、この2本のコードを接続することで内蔵HDD・SSDとして使用することができます。
電源用コードは増設HDD用としてパソコン内に用意されていることが多いですが、SATAコードは予備がない場合が多いため別途購入する必要があります。コードは数百円程度で買うことができます。
・追記
今回はパソコン内部にてSATAコードを使ってSSDを接続してクローンを作成する方法をとりましたが、上記のようなSATA → USB変換アダプターを使用してパソコンにSSDをUSB接続してクローンを作成することもできます。
このSATA → USB変換アダプターを使うことでノートパソコンでのクローンSSD作成もできますし、これがあれば2.5インチHDD/SSDを外付けデータデバイスとして使用することもできますのでクローン作業後もいろいろと役立ちます。
また、このSABRENTのアダプターはクローン作成ソフトが無料で使えることから、最近ではこちらのアダプターを使用する方法をおすすめしています。
今回の作業では個人データが保存されている別のHDDはそのままでWindowsのシステムデータがあるCドライブだけのHDD(使用データ数約30GB)をSSDに換装する作業でしたので、120GBもあれば十分足りる容量でした。
ノートパソコンやスリム型デスクトップパソコンなど内蔵HDDがひとつしかないタイプの場合は、保存している個人データ分も含めた全データ分が保存できる容量のSSDを購入するか、個人データを外付けHDDなどに移してデータサイズを交換するSSD容量以下にする必要があります。
例:容量500GBの内蔵HDDの場合
○ Windowsシステム+個人データの合計が数十GB程度 →120GBのSSDでOK。
× Windowsシステム+個人データの合計が約180GB →240GBのSSDを購入するか、個人データを外付けHDDなどに移動してデータサイズを小さくする。
実際に取り付ける際の注意点ですが、パソコンの電源コードを抜いた状態で作業をおこなってください。また、パソコン本体や各種パーツは精密部品ですので、静電気による故障を避けるために帯電にも気をつけましょう。
パソコンとSSDの接続確認
パソコンとSSDを接続し、パソコンを起動します。接続に問題がなければ外付けHDDを初めてパソコンに接続した時と同じように自動的に認識され「デバイスを使用する準備ができました」という通知が画面右下に表示されます。
また、スタートから「コンピュータ」を開き、「ハードディスクドライブ」欄に接続したSSDが認識されていれば接続は完了です。

デバイスマネージャー
もし認識されていない場合は、スタートから「コントロールパネル」→「ハードウェアとサウンド」→「デバイスマネージャー」を開き、ディスクドライブの項目内に取り付けたSSDが表示されているか確認してください。
SSDの名前が表示されてなかったり、SSDの表示に黄色のビックリマークなどがついている場合はうまく認識されていませんので、もう一度接続し直してみてください。
それでも認識できない場合は、SSDかコード、もしくは接続箇所などの物理的不良の可能性もあります。
次のページでは、HDDデータをまるごとSSDにコピー(クローン)する方法について説明します。